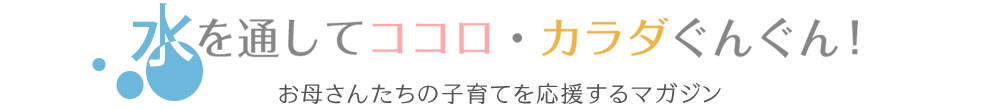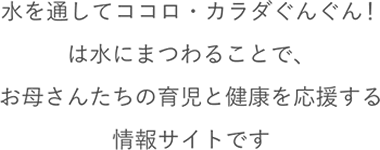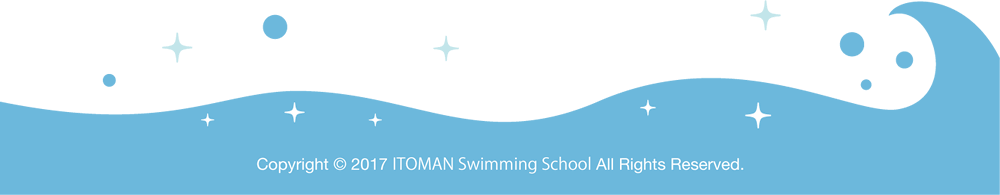2019.05.17 | 育児
“推測力”が不可欠! コミュニケーションの構造

子どものコミュニケーション力を育てる!【第1回】
情報などの伝達を意味する「コミュニケーション」。
「コミュニケーション力」とは、伝達や意思疎通をスムーズに行うために、言葉などを使って、自分の気持ちや意見を相手に伝える能力をさします。
企業が新卒者を採用する際にも「特に重視したい」項目として、毎年必ずあがっています。近年は、医学部入試でも話題になりました。
本シリーズでは、コミュニケーション力の発達の仕組み、家庭でどのように育てていくかを、言語とコミュニケーションの専門家である、東京学芸大学教授 松井智子さんに解説してもらいます。
言葉と心の理解からなるコミュニケーション
人に何かを伝える時には、表情、ジェスチャーといった非言語も活用しますが、重要なことを告げる際には必ず言語が用いられます。
そういった言語を核においたコミュニケーションは、
①当事者間で交わす言葉の正しい理解=言葉の理解
②会話の背後にある言語化されていない部分の推測=心の理解
という、2つの構造で成り立っています。
コミュニケーションを難しくするのは②心の理解の部分。
会話の背景をどれほど理解してやりとりしているかが意思疏通の質に関する鍵を握ってきます。
情報や意見、思いは、形があるものではなく、「心」に浮かんでいるものです。
私たちは、この形のないものに言葉を当てはめ、相手に伝えています。
しかし、言葉は心にあることをすべて正確に伝えられるほど、完璧な道具ではありません。
「心」に浮かんでいるものに対してぴったりと当てはまる言葉がみつからないことはたびたび起こることです。
そこで、言葉と心の中で思っていることのギャップを埋めるために、登場するのが「推測力」です。
私たちは、会話をする時に相手の言葉の背景にあるさまざまな要素(好み、それまでの発言、その人の経験・性格、家族の状況など)を思い起こし、それを手かがりにし、相手の「心」に浮かんでいるものを推測していきます。
会話がスムーズに流れる時、相手の言葉が理解できるだけでなく、相手の「心」に思い浮かんでいる背景・情景も同じように自らの心に描かれているはずです。

文脈を読み取らせる「話し手」、正確に読み取る「聞き手」
コミュニケーションには、伝える側<話し手>と受け取る側<聞き手>という役割があり、それぞれ求められる内容が異なります。
<話し手>には、伝えたいことを言葉にして、相手にわかるように知らせる力が必要とされます。
一方、<聞き手>は、聞いたことを正しく理解する能力が求められます。
話し手の心の中を推測し、言語化されていない部分を埋めるのは<聞き手>の役割です。
子どもは、まず<聞き手>として「話を聞いて理解する力」が発達していきます。
この力が伸びると<話し手>が担う「相手にわかるように話す力」も自然と向上していくのです。
スムーズなコミュニケーションに欠かせない背景の情報
コミュニケーションは、話し手と聞き手の相互協力のもとになされていきます。
ですから、話し手がわかりにくい言い方をしたり、聞き手の推測力が乏しかったりすると、意思疎通が難しくなる傾向が見受けられます。
<会話例> 金曜日のランチに関する会話
Aさん:「お昼はBさんが好きなパスタにしようか」
Bさん:「今週は、月曜日と水曜日にパスタを食べたわ」
★Aさん(聞き手)はBさん(話し手)の発言をどう捉えたらいいでしょうか。
<解釈1>
Bさんはパスタ好きだけど、今週はすでに2回も食べている。「和食も好きだ」と言っていた。「今回は、パスタはやめよう」ということだ。
<解釈2>
今週はすでに2回も食べたと、パスタ好きを強調。今回も「パスタ!」ということだ。
この2つはBさんがどのくらいパスタを好きなのかを知らないと、真意がくみ取りにくくなっています。
話し手がはっきりと「Yes」「No」を表明せず、間接的な言い方をすると、その分、聞き手が正しい文脈を選ぶ責任を負うことになる例でもあります。
情報が足りない場合は、会話を続けながら真意を探っていくのです。
心の中の推測は、大人であっても初対面の場合は難しく感じるので、子どもにとっては簡単なことではありません。
子どもたちは、言葉を覚え、実際に使いながら、さまざまな経験を重ねて、徐々に心の中の推測を含めコミュニケーション力を向上させていきます。
松井智子(まついともこ)さんのプロフィール
東京学芸大学 教授
早稲田大学卒業後、ロンドン大学に留学し、博士課程まで進む。
専門は認知科学だが、英語教育についても詳しく、自らの子育て経験を踏まえて語る内容に定評がある。
著書『子どものうそ、大人の皮肉』など。