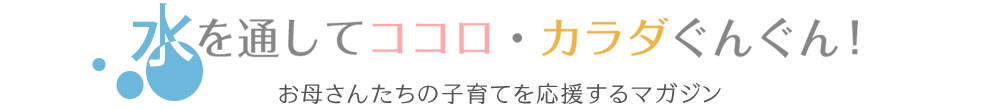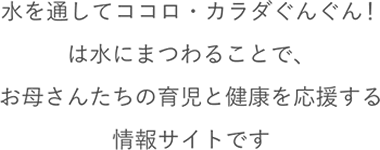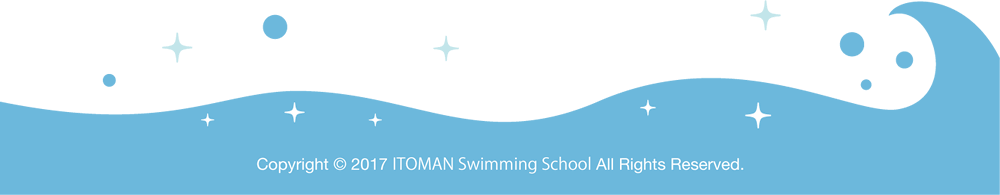2019.07.06 | 育児
コミュニケーション力が言語発達、感情コントロールを促進!

子どものコミュニケーション力を育てる!【第6回】
最終回は、コミュニケーション力が、言語力や感情コントロールなどとも深い関係をもち、子どものよりよい成長につながることについて説明します。
(記事監修/東京学芸大学教授 松井智子)
子育ては何があるかわからない!!
親がどんなに気にかけても、時に子どもはアクシデントに巻き込まれたり、思いもしないことをやってしまうもの。
そのことは、自らの子育てを通して強く感じています。
保育士や幼稚園の先生からの「“ちょっと”気になることがあるのですが・・・」で始まった言葉の真相を子どもに尋ねるのは気が重いもの。
子どもに上手に伝えて、しっかり対処していきましょう。
「今日、○○君とケンカしちゃったんだってね。何があったの?」と言いたい気持ちを一旦収め、「それ作ったんだ?上手にできたね」と、普段通りの会話から始めます。
そしてトーンを変えずに、「○○君、お帰りの時に悲しそうだったよね。お母さん、気になったんだ」と本題につなげてみてください。
子どもが語りにくい内容は、騒ぎ立てずに核心にもっていくのが鉄則。
この方法は、4~5歳ごろには特に有効です。
反抗期は、成長に必要なステップ
2〜3歳ごろに迎えるイヤイヤ期だけでなく、自分で考えて行動したい気持ちが高まる4~5歳や小学校低学年も、親の言動に素直に従えないことがあります。
しかし、10歳未満の子どもは、親を困らせようとして「いやだ!」と言っているわけではありません。
脳や心の発達に伴って生じる、自分では何ともし難い混沌(こんとん)状況にあり、その防衛手段として、その場しのぎの「いやだ!」が出てしまう。
「いやだ!」は次の成長段階に進むための必要なステップなのです。
こういうときの「いやだ!」には躍起にならずに、「そういう時期だからしょうがないな」と待つことで解決されることもあるはずです。

コミュニケーションと言語化、感情コントロールの関係
世話をしてくれる身近な人と親密な関係を構築し、その上に他者や自分への信頼感を積み上げていく。
これは子どもの成長に必要な愛着と呼ばれるものです。
愛着は、スキンシップやしがみつく・追いかけるといった行為を通して2歳ぐらいまでに形成されます。
言葉が出るようになると、愛着に代って言語を交えたコミュニケーションが親密な関係づくりに大きく貢献してきます。
子どもは信頼する人に感情表現をします。
そんな時には子どもの心の中にある“もやもや”などを受け止め、「今、悲しんだね」と的確に反応し言語化することで、 “もやもや”を外に出して心を軽くしてあげることができます。
「悲しんだね」という言葉から、子どもは「これが悲しいってことだ」と認識したりもします。
こうした経験を通して、心の整理方法や目に見えないものを言語化することを子どもは学んでいくのです。
的確に反応するのは簡単ではありませんが、子どもの言動を観察して心の中を推し量ることが手がかりになるかもしれません。
さらに、大人になるとより強く必要性を感じる怒りの感情をコントロールする方法も、こういった親密なコミュニケーション下で育てられる“言語化”が大きく寄与してきます。
子どもたちがムシャクシャした気持ちを、表に出さずに対処できるようにするポイントを2つあげます。
まずは、①怒っているその状態を子ども自身が客観的にキャッチできるようになること。
「今、すごーく怒っている!」と気づいて、「でも、ここで怒っちゃダメだ」と子ども自身が自分に言い聞かせることができれば、その場を離れるなりしてやり過ごすことができるはずです。
もうひとつは、②怒りの原因を説明できるようになること。
説明するのはお母さん、お父さん、友だちといった他人でも、自分自身でもいいのです。
話す時には少しばかり客観的になるもの。
「あんなことされて、黙ってはいられない!!」という思いをだれかに話すことで心の緊張から解放された経験がある方も多いと思います。
その点は子どもも大人と同じです。
気持ちが少々落ち着いたら「でも、私、なんでこんなに怒っているのかな?」と自分に突っ込みを入れられたら、目くじらを立てることではないかも・・・という考えがでてくるかもしれません。

①自分に「ここで怒っちゃダメだ」と言い聞かせる時も、②怒りの理由を説明する時も言葉を使います。
このように自分の気持ちを理解し、言葉で表現できることが、感情コントロールの第1歩といえます。
自分が置かれた状況を説明できずに混沌のなかに放置されたままでは、感情抑制が難しく、怒りで暴言や荒れた行動を起こすことになりかねません。
気持ちを表現する言語力も、感情コントロール力も皆、コミュニケーション力とリンクし、充実した人生を生きるための重要なスキルです。
その意義を早い時期から知り、一生をかけて親子ともに育て続ける。
それが親子のコミュニケーション力を強固なものにする気がします。
<完>